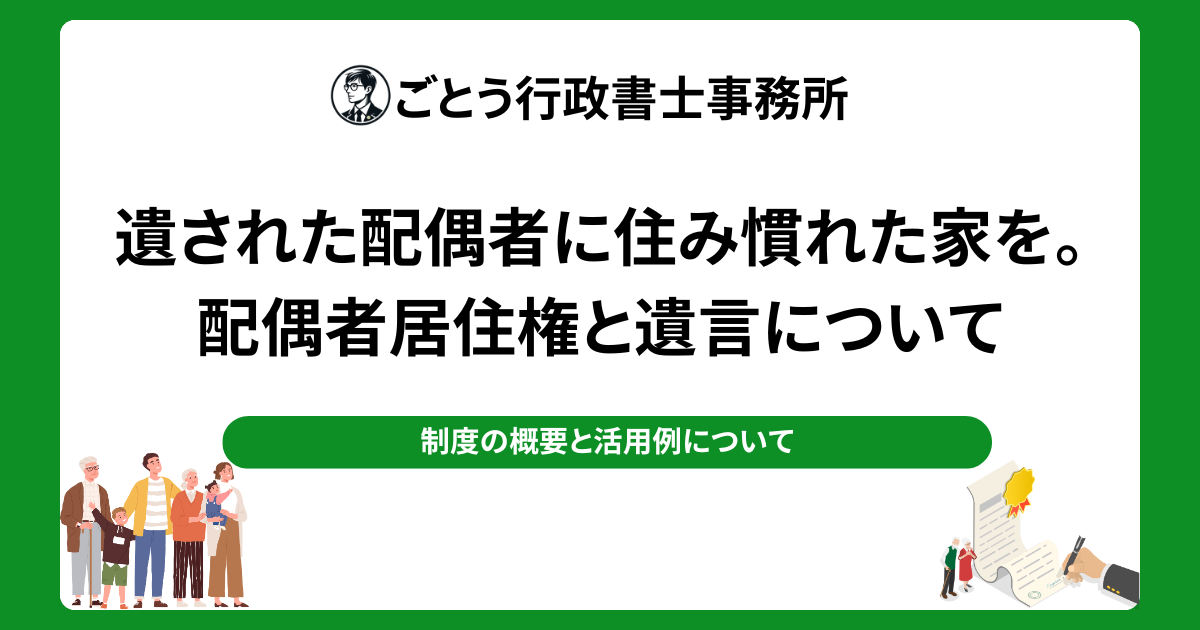遺された配偶者に住み慣れた家をーー配偶者居住権と遺言について
こんにちは、ごとう行政書士事務所の後藤です。

もしものときに、自宅を相続するとなると今後が大変そう…。でも今の家に住み続けたいんですけどどうしたらいいですか?
このようにお悩みになる方もいると思います。
これまでの制度では、「家=不動産」という財産を相続できなければ、住み慣れた家から出ていかざるを得ないケースも少なくありませんでした。しかし、2020年に民法が改正され、家を相続しなくても“住み続けられる権利”を保障する仕組みができました。それが「配偶者居住権」です。
この制度には、「短期配偶者居住権」と「配偶者居住権(長期)」の2種類があり、それぞれ制度の趣旨や適用条件が異なります。うまく活用すれば、配偶者の生活の安心を守りつつ、他の相続人とのバランスにも配慮した遺言を残すことができます。
本コラムでは、制度の概要と活用例をやさしく解説しながら、遺言書にどのように記載すべきか、注意点はどこかを行政書士の立場からお話ししていきます。
\ 遺言・相続でお困りの方はまずはお気軽にご相談ください。/
そもそも配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が 亡くなった人が所有していた建物に、亡くなるまで又は一定の期間無償で居住することができる権利です。
この制度は、2020年4月1日施行の民法改正によって新たに導入されたもので、以下のような問題意識が背景にありました。
- 高齢の配偶者が、自宅に住み続けたくても、自宅を相続できずに退去せざるを得ないことがあった
- 配偶者が自宅を相続する代わりに現金や預金を希望する他の相続人と折り合いがつかないことも多かった
- 長年住んできた家から離れたくないという配偶者の気持ちを保護する仕組みが不十分だった
こうした現実に対応するため、「自宅の所有権とは別に『居住する権利』だけを相続できるようにする」制度が設けられたのです。
制度の目的 ― 自宅を財産としてもらわなくても住み続けられるように
従来の相続制度では、自宅を「相続する」か「相続しないか」の2択でしたが、配偶者居住権の制度により、次のような柔軟な対応が可能になりました。
- 自宅の所有権は他の相続人(たとえば子ども)が取得
- 配偶者には「居住権」という形で、引き続き住む権利を保障
これにより、配偶者の生活の安定を図りながら、他の相続人との財産分配のバランスもとれるようになっています。
短期配偶者居住権と長期配偶者居住権の違い
配偶者居住権には、2つの制度があります。
一つは「短期配偶者居住権」、もう一つは「配偶者居住権(長期配偶者居住権などとも言われます)」です。
この2つは、権利が発生する仕組みや効果の持続期間が大きく異なります。
短期配偶者居住権(民法第1037条~1041条)
「短期配偶者居住権」は、配偶者が被相続人と一緒に住んでいた建物に対して、原則自動的に発生する権利です。
これは、相続人であるか否かにかかわらず、遺産分割が終わるまで、または相続開始から6か月間のいずれか長い期間、無償で住み続けることができます。
この権利には登記は不要で、あくまで一時的な居住を保障するための暫定的な制度です。
配偶者居住権(長期)(民法第1028条~1036条)
一方、「配偶者居住権(長期)」は、遺産分割協議や遺言によって配偶者に認められることで成立する権利です。
原則として配偶者が亡くなるまで、または遺言などで定められた期間、その建物に無償で住み続けることができます。
この権利は登記することで第三者にも対抗可能となり、不動産の売却や相続トラブルに対するも高まります。
また、配偶者居住権には評価額があるため、遺産分割の対象として、財産価値に換算される点も特徴です。
\ 遺言・相続でお困りの方はまずはお気軽にご相談ください。/
どんなときに関わるの?配偶者居住権が活きるケース例
これまでの説明を聞いて、配偶者居住権について「理論としてはわかったけれど、実際にどんなときに関係してくるのかイメージが湧かない」という方も多いかもしれません。そこでここでは、相続の現場で起こりうる具体的なケースをご紹介しながら、この制度がどのように役立つのかを見ていきましょう。
ケース1:ほぼ自宅しか財産がない家庭で、配偶者の生活費もきちんと確保したいとき
一般的なご家庭では「財産=ほとんどが自宅で、少しの預金」というケースが多いと思います。
現金や預金の額次第では、「配偶者が生活費を得る」「自宅を相続する」を両立させようとすると、他の相続人に公平に分けることが難しくなります。このようなときに
- 家の所有権は子に渡す
- 配偶者には居住権を与える
- 配偶者居住権の価値を踏まえて、現金を分割していく
とすることで、現金と「住まい」を分けて分配できる柔軟な対応が可能になります。
ケース2:再婚家庭など、法定相続人と関係性が薄い場合
再婚同士や事実婚に近い家庭では、子どもと配偶者の関係が希薄なこともあります。
「亡くなった後、相続人である子どもから家を出ていくよう言われたらどうしよう」と不安を抱く配偶者も少なくありません。このようなときに、遺言により配偶者居住権をしっかりと残しておくことで、
- 亡くなった人の意思として、配偶者がそのまま住み続けられることを法的に保障
- 相続人による売却や立ち退きの要求を防げる
といった安心材料になります。
遺言書に配偶者居住権を盛り込むときの注意点
配偶者居住権は、遺産分割や家庭裁判所の審判でも設定できますが、最も確実で意義のある活用方法は、被相続人が生前に遺言書で明示しておくことです。ここでは、遺言書に配偶者居住権を記載する際に、特に気をつけるべきポイントを整理してご紹介します。
その1:配偶者居住権を「遺贈する」と明記すること
まず最も重要なのが、遺言書の中で「配偶者に対して配偶者居住権を遺贈する」という文言をはっきりと書くことです。
この一文があることで、配偶者は相続人との協議を待たずに確実に住む権利を取得できます。
遺言書を作成するときに「相続させる」という表記をすることもありますが、配偶者居住権において「相続させる」という表記はNGです。この表記をしただけで遺言書が無効になるか否かは議論の余地がありますが、疑義を残さないためにも「相続させる」という表記をしましょう。
その2:税務面のリスクにも注意が必要
配偶者居住権は節税効果が期待される一方で、想定外の課税が発生する可能性もあるため、注意が必要です。
たとえば、配偶者居住権を持っている妻が老人ホームに入るなどして、その建物を第三者に売却する必要が出てきたケース。所有者である子どもが「売却のため、配偶者居住権を消してほしい」と依頼し、配偶者が無償または低額でその権利を放棄すると、贈与税が課税されるおそれがあります。
また、反対に子どもから一定の対価を受け取って権利を放棄した場合でも、配偶者側に譲渡所得税の課税対象となるケースがあるため、慎重な検討が求められます。
現行の制度では、本来物件売却時には使える特別控除(たとえばマイホーム売却時の3,000万円控除)が配偶者居住権には適用されない点も含め、今後の法改正や運用に注目が必要な領域となっています。
その3:負担の所在が不明確なままではトラブルに
本来であれば、固定資産税は物件の所有者が支払いを行います。そのため賃貸借契約であれば、借主が負担することはありません。通常の維持修繕費についても貸主の負担で行います。しかし配偶者居住権の場合は、配偶者が居住権を得た場合、その家の固定資産税や通常の維持修繕費は配偶者が負担することになります。
一方で、大規模なリフォームや災害等の復旧費用は、建物の所有者が負担するとされていますが、明確な線引きについてはまだ議論の余地のある分野です。
こうした負担の境界が不明確だと、「この修繕費は誰が出すべきか」といったトラブルにつながるおそれがあります。
さらに、配偶者が居住権を放棄して住み替える場合には、原状回復義務(きれいにして返す義務)が発生することもあり、思わぬ出費を招くこともあります。
その4:その他注意すべき点
配偶者居住権は強力な制度ですが、すべてのケースで遺言書によって成立するとは限りません。
特に以下のようなケースは、遺言に明記しても効力が認められないとされています。
- 対象の不動産が共有名義(夫と子など)で、被相続人単独の所有でない場合
- 相続開始時点で、配偶者がすでに老人ホームなどの施設に住んでおり、自宅に「居住していなかった」場合
- 婚姻関係にない内縁関係や同性パートナーなど、法律上の配偶者でない場合(現行法上)
- 制度施行前(令和2年4月1日以前)に作成された遺言書に基づく指定の場合
制度の適用には、細かい要件を一つひとつ満たしている必要があるため、遺言書を作成する際は、法律上の条件をよく確認しておくことが重要です。
配偶者居住権も含めた遺言書は、専門家(行政書士)のサポートを
配偶者居住権は、高齢化社会における大きな課題である「住まいの安定」を保障する、意義のある制度だと思います。一方で、制度の内容や適用条件、税務上のリスク、登記の必要性など、理解しておくべき注意点も多岐にわたります。
とくに遺言書で配偶者居住権を活用しようとする場合は、
- 対象物件の特定方法(登記簿上の表示)
- 遺贈の文言の正確さ
- 他の相続人の遺留分との調整
- 登記後の維持費や税務負担への配慮
といった点に注意しながら、制度に適合した遺言書の内容を設計する必要があります。
こうした場面で頼れるのが、行政書士をはじめとした専門家のサポートです。
当事務所では、
- 配偶者居住権を踏まえた遺言書の文案作成
- 必要書類の整理・財産目録の作成
- 相続人間の公平性を保つ文言の工夫/付言文案の支援
- 登記や不動産評価が関わる場面での他士業連携
などを通じて、依頼者の「思いが伝わる遺言書」を一緒に作成していきます。
また、相続税の影響が気になる方には、相続税を専門とする税理士事務所と連携していますので、税務面も含めたトータルなサポート体制を整えています。



配偶者が安心して暮らし続けられるように



家族が相続の時に争ったりしてほしくない
そう願う方こそ、一度この制度を知ったうえで、遺言書を検討するのには意義があると思っています。
制度の理解と遺言の工夫で、安心を遺言書という「かたち」に残すお手伝いができますと幸いです。
\ 遺言・相続でお困りの方はまずはお気軽にご相談ください。/